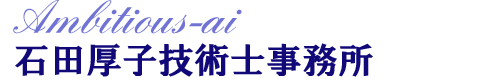イタリアで行われている冬季オリンピックの話題で日本中が湧いている。テレビをつければ、どこのチャンネルもオリンピック一色である。実は、私はスポーツのニュースが苦手である。選手たちの活躍の映像とともに流れる「不安と恐怖に打ち勝って」という言葉に胸を締め付けられて、つらくなるからである。
自分の信念に従って行動する「高い志を持つ、市場価値の高い技術者」を育成します。
コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

コラム
月曜日に初めての場所に行く

小さなご褒美小さな幸せ

今年(2026年)に入って1か月以上過ぎた。いろいろなことを詰め込みすぎて、頭と体が爆発しそうだった。そのせいか、ここのコラムの内容も、1月の半ばからかなり無理をしている様子が見て取れる。書き手としても読む人にも重苦しさを感じさせるだけなのに。
悩むということは生きている証

最近、夜中に目覚めて、それ以降、眠れなくなることが多い。その間、様々な不安な事が頭をよぎる。それらはすべて、今年になって新たに始めたことに関わることである。
いくつもの顔を持つということ

このコラムで、今年(2026年)の目標は「新しいコミュニティに入る」そして「新しいことに挑戦する」だと(しつこく)書いてきた。毎年のことだが、目標を立てても掛け声ばかりで月日が経ってしまうことが多い。しかし、今年は1月のうちにそれらが現実になってきた。
受身からの脱却にはエネルギーがいる

時々、企業に勤めていた頃の「組織の掛け声」を思い出す。例えば、「リアクティブからプロアクティブへ」と盛んに言われていたのはいつだっただろうか。仕事をする上では、言われたことだけを粛々とこなすのではなく、自分から積極的に仕事を開拓せよ、ということか。
体験的お酒の功罪

かつて、仕事上の付き合いのある人から「自分はお酒好きではあるが、依存症ではない」と主張されたことがあった。これは難しい問題だ。多分、『お酒好き』と『アルコール依存症』の境界は、かなり曖昧ではないかと思う。
私はどこの国の人

2026年が始まった。今年の目標は、「初めてのことをすることによって脳に刺激を与える」にしている。でも、もう一つ付け加えよう。「物事をより柔軟に考える」である。これまでの常識、こだわり、しがらみから解き放たれた、何でもありの考え方を加速させよう、ということである。
脳に刺激を与える良い方法

例年より早い12月15日に年賀状を投函した。会社勤めをしていた時と比べればかなり減ったが、毎年欠かさず出している。多分、(認知機能が衰えていない限り)一生出し続けるだろう。
存在していなかったものを作り出す力

十数年前に、TRIZという理論(発明技法とも呼んでいた)の利用法について検討する仕事をしていた。TRIZは過去の膨大な発明(特許など)を分析し、新たなものを発想する思考のパターンを分類し、それを利用して次の技術の創造や発想をする技法である。
インドで70年前の日本を思い出した

前回のコラムで述べたように、2025年11月下旬、インドの南部の都市ベンガルールの企業と大学を訪問した。世界で活躍しているIT人材を輩出しているインドの教育事情を知り、世界とのネットワークを拡大しながらビジネスを進めていく勢いに驚かされた。
インドの大学の勢いに圧倒される

今年(2025年)11月の最終週に、インドの南部の都市ベンガルール(バンガロール)の企業と大学を訪問した。ベンガルールは「インドのシリコンバレー」と呼ばれている。南インドの1都市を見てインドを知ったとは決して言えないのだが、現在のインドの一端、特に成長の勢いを知ることができた。
人間も同じ生き物なのだ

Suicaのペンギンが消える、と聞いてショックだった。ペンギンという鳥に思い入れがあるわけではなく、Suicaのキャラクターが変わったからと言って生活が変わるわけでもないのに、寂しさは拭えない。パンダが日本から居なくなるかもしれないと聞いて、何とかならないのか、と思う。
流行語とは何なのか

朝、目覚める直前に何かを思い付く。半分は夢の中である。それは、現在勉強中のヒンディー語の言い回しだったり、今日やるべきことだったりする。何かが閃く(ひらめく)、といった大げさなことはほぼない。
よいコミュニケーションの取り方は様々

その日は三連休の初日で、地下鉄はとても混んでいた。何とか滑り込んで、人の隙間から手摺を掴むことができた。優先席の3人掛けの席に、小さな子供が2人と家族ではない大人が座っていて、その間に座れそうなスペースがあるのが見えた。
違和感は常識を変えるチャンス

日本で女性初の総理大臣が誕生したことで、新政府への期待が高まっている。少なくとも、その雰囲気がメディアに溢れ返っている。ただ、どうしても違和感を覚えざるを得ないことがある。
想像力はなぜ劣化するのか

来月(11月)、インドのバンガロールを訪問する。ここはインドのシリコンバレーとも言われている地域であるので、情報産業に携わってきた者としては、ぜひ実状を知っておきたい。
欠点が強みに変わるとき

今年(2025年)、日本では2人の研究者がノーベル賞を受賞した。混沌とした社会情勢に翻弄されている現在の日本にとって、明るいニュースである。
切り取られた風景

スマホの壁紙を、風景写真がランダムに表示されるよう設定した。数時間おきに切り替えられる写真は、見たこともないものばかりである。最初は、著作権で縛られていない海外の写真をランダムに出しているのだと思った。
これが本当の潮時か

自宅の洗濯機が突然エラーを発するようになった。マニュアルを読むと、コンセントを抜き差しても同じなら故障なので修理する必要があるとのこと。そのとおりやってみたら動いた。ほっとしたのも束の間、数日後同じ現象が起きた。今度は数回の抜き差しが必要になった。
終わった先にあるもの

インターネットで「終わった」という言葉から始まる記事の見出しを見つけた。その後には、親の介護や家族の問題が続いている。とっさに、これは良いニュースだと思った。
いつの間にか変わっている

ウォーキングしていて汗をかかなくなった。まだ猛暑を引きずった残暑が続いているはずなのだが、涼しく感じられる。考えてみたら2つのことに気づいた。まず、汗をかいてはいるのだが、風がよく吹いているのですぐに乾いてしまう。
人生の逆転劇と逆転しない正義

関東に住む私は殆ど見たことがないのだが、関西万国博覧会の公式キャラクターであるミャクミャクがかなり流行っているらしい。当初これが発表されたときは、「なんと気持ちの悪い」と思った。多くの人もそう思っているはずだと勝手に決めつけていた。
戦争体験者の声をあえて聴かないこと

9月になったが猛暑は終わらない。ただ、吹く風はなぜか涼しくなったような気がする。過ぎて行った8月は、80年前に2つの原爆が投下され、第2次世界大戦に敗戦した、日本にとって忘れがたい月である。
知らずに誰かを傷つけていなかったか

同年代の後期高齢者と話をしていると、過去のある時点での意思決定が間違っていたのではないか、ということを言う人がいる。例えば「あの時、別の選択をしていれば今はもっと良くなっていたのではないか」といった意味の後悔の念をつぶやく人が、少なからずいる。
夢があるから動き出せる

猛暑のせいなのか、ひょっとしたら年齢のせいなのか。最近、行動を起こすまでに時間がかかる。腰が鉛のように重くて、足を踏み出すのがつらい。動かなくて済む理由を必死で考えている。
終活は元気な時に始める一大プロジェクト

この夏、77歳の誕生日を迎えた。80歳前後には大きな壁があるような気がしている。上司、友人などが次々と亡くなっているからである。私は大丈夫などと言ってはいられない。
複雑なことを単純にしてはならない

最近、どう考えても単純と思われることを複雑にして、時間とコストを無駄遣いすることが目立つ。例えば、某市長の学歴詐称など、一見すれば誰も問題にしないであろうことを、日本中で大騒ぎしている。できるだけ自分が傷を負わずに現状維持したまま、嵐の去るのを待っている「保身のため」としか思えない。真実はひとつなのに苛立たしい。
栄養補給と不安解消で猛暑に勝つ

情けないほど体が疲れている。何もする気が起きない。何かをした後はさらに疲れる。これが6月から続いている暑さのせいであることは明らかだ。8月生まれの私にとって、夏こそが最も活発に動ける季節だったはずなのに。やはり老いには勝てないのか。
会話が成り立たないのは何故だろう

現在の私の課題は、他人との会話の機会を増やすことである。家族と暮らしていた頃、企業や大学に勤めていた頃は、朝から晩まで誰かと会話していた。それが今はどうだ。誰とも話をしない、一人静かに過ごす日々の何と多いことか。
希望的観測に振り回されるな

現代は予測不能なことが多すぎる、と最近強く思う。世界中の殆ど全ての問題は正解がないとしか言えない。なぜなら、いつも自分の予測が外れるからである。例えば、8年前米国の大統領選挙では、まさかトランプが当選するとは思わなかった。
熱中症との戦いはまだまだ続く

6月から異様な高温が続き、体は悲鳴を上げている。今年は、幸いなことに、ウォーキング中に脚が攣って歩けなくなる、めまいを起こして電柱にしがみつくなどということは起きていない。
スマホにマイナンバーカードを入れてみた

ニュースでiPhoneにマイナンバーカードが入れられる、ということを知った。入れられることの意味、つまりそれでできることについてはよくわからない。それでも、新しいことはとりあえずやってみよう、と飛びつくのが私の悪い癖である。すぐにネットで検索し、登録方法を頭に叩き込んだ。さらに、動画も観てイメージトレーニングを行った。
未来を担う人に望むこと

もしも生まれ変われるとしたら、研究者になりたい。テーマは何でもよい。宇宙、地球、生物、人間・・・。それらの本質的なもの(真実)を掴んで、さらなる未知なものを探っていく。最終的には、地球が安全かつ豊かになるのに役立つ何かを見つけ出したい。
お酒を飲まなくなったのはなぜか

高齢になれば好みが変わることがあるとしても、これは奇跡である。気づいたら、全くお酒(アルコール飲料)を飲まなくなっていた。何十年もの間、毎日晩酌を欠かさなかった。
全ては地球規模の問題

その昔、「この海の向こうにはアメリカがあるのか」、「この空はどこかの国とつながっているんだ」と様々な思いを持ちながら景色を眺めていた。一方で「そこに行くチャンスは自分には一生来ないだろう」とも思っていた。
備蓄米と初任給

2025年6月初めは、コメの価格高騰に対処するために政府が備蓄米を放出し、それが迅速に大手スーパーやコンビニに並ぶようになったニュースで溢れかえっている。
誰かに制御されてしまう恐ろしさ

なぜ、ネット上の嘘の情報を信じてしまうのか。他の情報をよく調べればわかるはずなのに。なぜ、詐欺の電話にひっかかってしまうのか。あれほど警察やマスコミが注意を促しているのに。
次は無いかもしれない

ずっと自分は長生きできるような気がしていた。父は10年前に97歳で天寿を全うしたし、母は100歳を超えて高齢者施設で暮らしている。その子供なのだから。しかし、たとえ長生きできたとしても、私が望んでいる姿、すなわち「生きがいを持って幸せに暮らしている」になっているとは限らない、と最近感じ始めた。そのきっかけは2つある。
絡まった糸はどう処理するか

仕事部屋の中にはコード類が沢山ある。それらは互いに絡みあっている。コードの端には扱いに注意すべき電子機器があるので落ち着いてほどかなければならない。注意深い行動も認知症予防にとって大切だ。
贅沢は人それぞれ

私にとってお金がかかるものはすべて贅沢に見える。食料品はすべて、数年前と比べれば贅沢品である。でも、生きていくためには食べる必要があり買わざるを得ない。ただし、同じ「食」でも手が出ないと避けているものはある。外食、フルーツやスイーツなどである。
信じたい気持ちは真実よりも強い

ネットの世界には真実の情報だけではなく偽の情報が多く存在する、と誰もが知っている。AIの発達によって、偽の情報がより真実と区別がつかない状態になっているということも、大半の人が認識しているはずだ。
問題が見つかってよかったじゃないか

トラブルというものはいつ起きてもおかしくない。年齢を重ねると失敗の事例が積み重なって、その思いが強くなる。特に新しいことを始めるときは、何か悪いことが起きるのではないか、失敗するのではないか、と考えてしまう。
人間は最期にどこに行くのか

昨年(2024年)夏、母が100歳になった。年が明けたころ、母の入っている特別養護老人ホームから連絡があった。昼間も寝ていることが多くなったということである。高齢なのでこれから何が起きても不思議はない。
柔軟性とネットワークが求められる時

目まぐるしく環境が変化する今日この頃である。当たり前だった四季は今やどこへ行ったのか。冬が過ぎればすぐに夏。夏が過ぎれば秋は一瞬で過ぎて冬になる。子供のころ学校で習った事の多くは変わっているらしい。
補い合うことで実現できること

最近、多言語学習のコミュニティのイベントで、複数言語を使ってシリコンバレー訪問の報告を行った。使ったのは、トルコ語、インドネシア語、ポルトガル語、英語である。2か月前から準備をした。
令和にパソコンと名刺はどう変わったのか

この1か月の間に満を持して(?)購入したものがある。一つはパソコンである。令和になって購入し、各々不具合を抱えている2台のパソコンを、これ以上悪くならないよう祈りつつ使っていた。しかし、仕事に差し支えることが明らかになってきたので、最後の手段をとった。
知識を得ても痛みは消えないが

2週間ほど前に、左側の背中から脇、胸にかけて痛むようになった。さらに時期を同じくして、右肩の痛みで腕が上がりにくくなった。76歳にして50肩か?ところが、これらはほんの3日ほどで消えてしまった。もちろん何もしないでいたわけではない。
旅先での小さな発見

3月の初旬、九州で仕事があり、2泊3日の旅をした。私は、陸路で行ける範囲であればできるだけ鉄道を使う。「車窓鉄」と勝手に称している。今回は博多と大分が目的地だったので新幹線と在来線を使った。この旅では思わぬ小さな発見がいくつかあった。
許容レベルを変えるとどうなるか

かつて(若い頃)は物や事に何かしらのこだわりを持っていたが、最近は殆ど消えてしまったような気がする。例えば食べ物であれば、体に悪いものが入っていなければ、別にどのブランドであるか、生産地はどこかなどあまり気に留めなくなっている。
機械は人間の言葉を理解しているのか

今回のテーマはAIに関することではない。言ってみれば、世の中でよく言われる「家電あるある」の話題である。すなわち、動かなくなった家電に、「新しいの買っちゃおうかな」などと話しかけると急に動き出す、といった現象に関する話である。
星の庭園

言語は不思議だ。通常は単なるコミュニケーションの手段としてしか見られていない。しかし、もっと違った力を持っているように思える。たとえ意味が分からなくても、耳から入ってくるだけで様々な感覚を呼び覚ます。例えば、ある言語は心地よさを感じさせる。
久しぶりにカワセミに出会う

寒波が1週間以上続いていた。外に出るのがつらい。それでも、ウォーキングしなければ歩けなくなってしまうかもしれない。過去の日記を読み直してみると、つい昨年まで、真冬でも、大学の教員として忙しくても、毎日2時間半のウォーキングをしていた。
記録は記憶を呼び起こす

下の子が11歳になった日から日記をつけ始めた。あれから30年以上続けている。10年日記が3冊となり、その後5年の卓上日記に変えた。最初は鉛筆書きで内容もメモ書き程度だった。そのうち、万年筆を使うようになり、内容も増えてきた。時々、その日と同じ日付の箇所とその周辺を読みながら、時の流れを感じたりしている。
働かないで済む理想の社会

少子高齢化が進み、15歳から64歳までの生産年齢人口が減少している。それがさらに進むであろうことも事実である。それに対処するためには、労働力人口(働いている人と働く意思のある人)を増やさなければならない。
人は本音で生きられる機会を求めているのか

毎日の生活の中で無理して、良い人でいようとすることは無いだろうか。私は、会合などで小さな子どもたちが大声でどなりながら走り回っていたり、下校途中の小学生が猛スピードで走っていたりするのを「ほほえましく眺めている優しいお婆さん」を演じているが、本音では、ぶつかられたら「私が」倒れてケガしてしまうかもしれないと恐れている。
コンサルティング会社はなぜ倒産するのか

最近(2023年頃から)、企業経営コンサルティング会社と言われる企業の倒産の数が増えてきているというニュースが良く見られるようになった。コンサルティング会社というと外資系の大手コンサルティングファームしかイメージしていなかったが、国内には様々な企業経営コンサルティング会社があることに気づいた。
規模拡大から価値拡大へ

2025年が始まった。1年前に何を考えていただろうかと2024年のコラムを読んでみた。そこで気づいたのだが、AIというものに対して危機感を抱いていたようだ。
今年挑戦したい生きるために大切なこと

最初に言い出したのが誰かは知らないけれど、「高齢者にとって大切なことは、キョウイク(今日、行くところがある)とキョウヨウ(今日、用事がある)」を多くの人から聞かされた。なるほど、と感心して聞いていた。
新たに始めたこと再開したこと

この数年、できないことや止めざるを得ないことが増えてきている。それに対して、新しいことを始めればプラマイゼロになる、と気づいたのは3年位前だった。何より、新しいことはゼロからの出発なので、どんなに小さな成果であっても感動の大きさはそれ以上である。
世の中からニオイが消えていく

大手製造業の管理職をしている人から聞いた話で驚いた。その人は、物質の組成、すなわち化合物の構成成分とその量の割合、から臭いを数値化する技術について調査しているとのことである。その人の会社は製造業ではあっても薬品や化学物質を製造してはいない。
挑戦すれば半分成功したようなもの

年齢を重ねるにつれて、何かをするのに「やらない方がよい理由」をつい見つけようとしてしまう。例えば、ウォーキングであっても、暑いから、寒いから、風が強いから、雨が降りそうだから、等々、いくらでもある。最近は、「ときめかないから」などという理由を作って逃げ出すことまで加わった。
多言語と多様性が創造力を高める

先週のコラムでも書いたが、今年(2024年)の11月にサンフランシスコとシリコンバレーの企業や自治体を訪問し、先端的な技術の開発と適用について情報収集してきた。
私の目と指が教えてくれた次の技術

11月の下旬、サンフランシスコとシリコンバレーの企業や組織を訪ね、先端ITの動向を調査してきた。帰国前日のことである。次の訪問先とのミーティングの前に、一緒に行ったグループ全員が昼食を取っていた。
壊した後どうするのかが問われる

NHKの朝ドラを毎日観るようになったのは、フルタイムの仕事を辞してからである。5年以上経つので、ドラマの数は10を超えている。次第に、ドラマに対する自分の好みの傾向が見えてきた。
遊びとビジネスの差はどこにある

長年生きていると、自分の性格についての認識が固まってくる。例えば、私は飽きっぽく、一つのことを集中して行うことが苦手である。若い時から、長時間実験したり、突き詰めてものを考えたりすることが得意ではなかった。
万人の理解と納得を得るのは難しい

政治関係のニュースを見ていていつも疑問に思うことがある。何かしらの疑惑が持たれている人に「説明責任を果たすことを求める」とはどういう意味だろうか。単に、状況を説明すればよいわけではないだろう。最終的には、相手が説明内容を理解し、納得することだろう。
今ってこうなっているのか

毎朝飲むコーヒーは、中挽き・中煎りのレギュラーコーヒーと決めている。味、香り、産地などに特にこだわりはない。安いものを近くのスーパーで買っているだけである。切らしかけていたので買いに行ったら売り切れだった。
占いとAIと創造性

易の勉強をしている人から占いの話を聞いたとき、あることを思い出した。それは、かつて文化人類学や民俗学の本を読んでいてなるほどと思ったことである。太古の昔から多くの地域で重要な意思決定に様々な占いが行われていた理由の一つに、思考のランダム化があったということである。
これまでの60年間とこれから

今年は新幹線が開通して60年とのことで、60という数字が何となく目に付くようになった。2か月前に76歳になった私の目線で60年間を考える機会も増えてきた。当時16歳の高校生だった私に、60年はどのような変化をもたらしただろうか。
説明できないことは教えられない

世の中には学校で習った程度の知識では理解できないことが多すぎる。例えば家電品は突然おかしな動きをして使えなくなる。我が家にあるものは、殆ど数年前に娘から譲り受けた中古品で2010年前後に生産されたものなので、原因を究明するまでもなく諦めるのが正しいやり方だ。
ジジババ上等じゃないか

土曜日の朝に楽しみにしている旅番組がある。最近、27年以上MCを務めていた俳優のKが番組を降りた。この1、2年のうちにみるみる痩せて髪は白くなり、直視できないほどの変貌ぶりだった。
私が仕事で筋を通してきたもの

学校を卒業し仕事をするようになって50余年経つ。一貫して情報技術(IT)関連の仕事に携わってきた。でも、仕事というものは自分で選ぶことは少なく、大半は与えられたものをこなすことが多い。
秋の訪れは考える力を蘇らせる

私はずっと冬に弱かった。寒さの中では頭が全く働かず、冬眠したいといつも思っていた。それに引き換え、8月生まれということもあり、夏には強いと思っていた。しかし、後期高齢者の現在は全く違う。暑さにめっきり弱くなった。
正座はできても全快とはならないのか

後期高齢者の現在、若い時とは大きく違うと感じるのは「病が治っても元には戻らない」ということである。若い時(65歳未満)は、病気やケガをしても、これが治れば元の生活に戻れる、ひょっとしたら以前よりも健康になるかもしれない、という期待をすることができた。
復活の日に思う

特別とも言えないある日の訪れをこれほど心待ちにしたことがあっただろうか。どれほどかというと、その日の未明に眠い目をこすりながらパソコンを立ち上げ、思わず万歳を叫んだ位である。それは今年の9月1日、私のギガ復活の日であった。
総合的な判断をする難しさ

日経新聞を電子版で読むのが毎日の習慣になっている。週末や月曜日にはレポート的な記事が多く見られる。科学技術に関する解説記事が多く、興味深く読んでいる。他にも、これまで報道されてきた一見無関係と思われるニュースを俯瞰的に眺め、それらの共通点から本質的な要素見いだそうというものもよく見かける。
眠りながら風を感じる

夜中に目が覚めた。おかしな夢を見ていた。どこかの子供と人間とロボットの違いはどこにあるかについて語り合っているらしかった。私は「ロボットは仕事をしていない時に電源を切っておいてもまた起動させることができるが、人間は死んでしまったらもう生きかえることはない。
将来を担う子供たちに何を渡すべきなのか

最近、いかに自分が多くのものを両親はじめ先輩方から受け取ってきたかを強く意識するようになっている。その量は、幼稚園から大学までの教育機関で受けたものよりも遥かに多く、影響力の多いものである。
猛暑の攻防戦

オリンピックの話ではない。毎年、猛暑の時期に遭遇する「電子機器の不具合との戦い」である。この数年は恒例行事のようになっていた。このコラムで何度も取り上げたパソコンの熱暴走は完全に私の負けだった。
何を増やし何を減らすか

あと何年生きられるだろうか。有限であることだけは確かである。一方で、これからの人生で使える資産が有限であることも確かである。地球レベルで限られた資源をいかに減らさず有効に使うか、を考えることは現代の大きな課題である。
今年の夏を満喫する

頂き物のそうめんをゆでて、何種類もの夏野菜をきざんでたっぷりと乗せる。ゆで卵を乗せて、麺つゆと酢をベースにした自家製のたれをかけて食べる。練り辛子が刺激になる。ああ夏だな、と実感する。
体力は気力より先に衰える

温暖化の影響か、熱中症の危険は早い時期から訪れ、脅威の度合いは年々高まっている。一方で我々の知識も豊富になり、熱中症対策も年々高度化(?)している。私も、今年からは温度と湿度の両方を計測できる機器を複数設置し、その数値を見ながら、エアコンの除湿、冷房、送風を使い分けるようにしている。