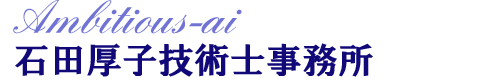最近(2023年頃から)、企業経営コンサルティング会社と言われる企業の倒産の数が増えてきているというニュースが良く見られるようになった。コンサルティング会社というと外資系の大手コンサルティングファームしかイメージしていなかったが、国内には様々な企業経営コンサルティング会社があることに気づいた。それらの倒産が増えているということは、何かビジネス面で大きな動きがある兆しを示しているように思える。
企業経営コンサルティングというと、まず思い至るのが「経営分析手法」である。私も企業に勤めている頃にそれらの教育を受けた経験がある。例えば次の手法が思い出せる。
・3C(Customer, Competitor, Company) ・4P(Product, Price, Place, Promotion)
・5F(競合の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威)
・SWOT分析(Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
・PEST分析(Politics, Economy, Society, Technology)
・PPM分析(花形、金の生る木、問題児、負け犬)
今改めてみてみると、PEST分析を除けばほぼ自社を中心にした分析である。PEST分析も新聞の記事カテゴリーにしか見えない。本当に役立っていたのだろうか。
一方で、現代の経営環境は大きく速い変化の波にさらされている。例えば、「価値の多様化」「予測できない天災、政治的な変動、戦争」「予測できない技術革新」である。上記の経営分析手法では、現状分析はおろか有益な対応策が発想できるようには思えない。最新のAIに聞いた方が、より広い視野から有益な分析結果やアドバイスが手に入れられそうである。
かつて勤めていた企業には外資系のコンサルティングファーム出身の同僚もいた。彼らの強みは、コンサルティングの経験と人脈だった。果たして、現在でもそれらは役に立っているのだろうか。例えば、グローバル環境における情報量は格段に多くなっており、個人の人脈の範囲を超えていないか。ビジネス環境の変化は加速しており、これまでの経験が生かせる範囲は少なくなっているのではないか。価値が多様化しており、それらの把握が困難ではないのか。何より、予測できないことが起きる可能性が大きい時代において求められる得意分野、専門知識、スキルの量や質がとてつもなく大きくなっている。とても過去の経験や個人の持つ人脈で対応するのは難しいのではないか。
こうして見てみると、コンサルティング会社の倒産問題は、他の業種にも当てはまりそうである。例えば、もう一つ最近の話題になっている「学習塾の倒産」がある。これも、世の中の変化の速さ、価値の多様化、予測できない事態、技術革新のスピードが関係している。であれば、それ以外の業種も同じ問題に直面せざるを得ない。
結局、コンサルティング会社のみならず、企業は統合に進まざるを得ないのではないだろうか。情報、知識、人材、経験を統合し、新たな価値を提供できるようにしなければ生き延びられないと思う。環境変化は随時起こりうるので、提供するサービスもかなりの頻度でアップデートを繰り返す必要がある。ビジネスモデルにも柔軟性が必要だ。
自分の信念に従って行動する「高い志を持つ、市場価値の高い技術者」を育成します。
「市場価値の高い技術者の育成」を目指して、
コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

トップページ > コラム
コンサルティング会社はなぜ倒産するのか
2025.1.19