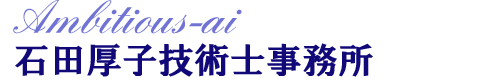現在の私の課題は、他人との会話の機会を増やすことである。家族と暮らしていた頃、企業や大学に勤めていた頃は、朝から晩まで誰かと会話していた。それが今はどうだ。誰とも話をしない、一人静かに過ごす日々の何と多いことか。このままでは認知機能が衰えてしまう。危機感を持つようになった。会話の機会は待っていても訪れない。
そこで見つけたのが多言語学習である。そのコミュニティでは多くの会話がある。それが非常に楽しい。外国語を聴くのもしゃべるのも不得意な私は日本語での会話が多いが、とがめられることはない。自分で話すよりも他の人の話を聴く方が多い。それでも、話した後、聴いた後のすっきりした気分、会話の内容の反芻まで、幸せな時間が続く。
一方で、わが子との日常会話、会議での仕事に関する会話、近所の人との会話などで、思うように意思疎通ができずいらだつ経験もする。会話が成り立たないのである。その際の会話の相手の年代、会話の内容は様々である。会話が成り立たない時は、つい私自身も支離滅裂なことを言ってしまうことが多い。ますます会話はおかしな方向に行ってしまう。最終的には「ああ面倒くさい」「もう二度と話したくない」とまで思ってしまう。
なぜ、楽しい会話と面倒くさい嫌な会話があるのだろうか。その違いはどこにあるのか。まず、会話の相手の年齢、相手との距離の近さは全く関係ないのは確かである。楽しい会話で上げた多言語のコミュニティは、様々な年代の人の集まりである。一方で、会話が成り立たないケースでも、若い人から高齢者まで様々である。相手との距離でも、初めて会った人とでも会話が弾むことがある一方で、家族のような近しい関係でも会話が成り立たないことは多い。やはり、コミュニケーションの取り方、技術の問題ではないか。
まず、多言語学習のコミュニティでの会話がなぜ楽しいのか、考えてみる。会話には話し手と聴き手が必要である。話し手の方は、必ずしも上手とは言えない。慣れない外国語を使うことが理由の一つとしてあるが、日本語でもうまく伝えられない時は多い。一方、聴き手側に回ると、一所懸命に相手を理解しようと努める。外国語の場合はもちろんだが、日本語でも同様である。相手の言っていることが分からなければ質問をする。それでも理解できなければ質問の仕方を変えて聴き出そうとする。ここが阿吽の呼吸では会話できない多言語学習のコミュニティならではの特徴である。最後に相手の言っていることが理解できるのですっきりする。話し手も自分の思いが伝わったと感じるので嬉しくなる。
会話が成り立たないケースは全く逆である。話し手は自分の思っていることを一方的に話す。時には感情的になってまくしたてる。聴き手もまた感情的になって防戦する。大抵は相手を否定する。話し手は、相手に分かってもらえないと思うと「別の話」で攻撃する。聴き手は話題が変わったのでますます理解できなくなり、さらに混乱する。
会話を成り立たせ、相互の理解を深めるのに大切なことは、相手を理解しようと努めることだと改めて思う。言葉を攻撃のための武器として使ってはならない。相手は分かるはずと思い込んではならない。話し手、聴き手のどちらの立場でも努力することが大切である。
自分の信念に従って行動する「高い志を持つ、市場価値の高い技術者」を育成します。
「市場価値の高い技術者の育成」を目指して、
コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

トップページ > コラム
会話が成り立たないのは何故だろう
2025.7.27