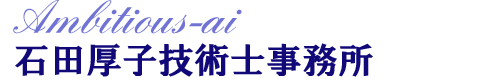目まぐるしく環境が変化する今日この頃である。当たり前だった四季は今やどこへ行ったのか。冬が過ぎればすぐに夏。夏が過ぎれば秋は一瞬で過ぎて冬になる。子供のころ学校で習った事の多くは変わっているらしい。景気の行方は予測ができない。変わらないのは年寄の意識だけかもしれない。変化は体調を悪くし、ついていけないことへのいら立ちは増すばかりだ。しかし、このままではいけない。我々は、もっと柔軟に変化に対応し、変化を糧にして成長していかなければならない。そんなことを考えながら、半年間止めていたNHKの朝ドラ視聴を4月から再開して大いに楽しんでいる。
普遍的な何かがあって、それを信じていればよいのであれば生きるのは楽になるかもしれない。宗教などはどちらかというと普遍的なものが存在することを前提にして、信者はそれを信じている人たちのように思える。宗教とまでは行かなくてもそのような傾向は至る所に存在するのではないか。私自身はそのようなことからは距離を置きたいと思っている。行動を何かに決められたくない、意思決定の柔軟性を奪われたくないからである。統計的数値に縛られることも同じ理由で嫌いだ。今日の常識が明日は非常識になるかもしれない。とても実現しそうもなかったことが、新しい技術で実現してしまうかもしれない。権威ある誰かの示唆ではなく、現状について自分で考え、最適と思える行動を取りたい。
最近、「言語の力」(ビオリカ・マリアン著,KADOKAWA,2023)という本を読んだ。その中で、人間の脳の言語処理機能はオーケストラのようなものということが書かれていた。その際、異なる言語は別々の楽器に対応するのではなく、オーケストラが演奏する楽曲に対応するというものである。そこで私の頭にはあるイメージが湧いた。人間が多言語を習得するのは、脳の機能を柔軟に組み合わせることにより、オーケストラが様々な曲を演奏できることという認識である。多くの楽曲を演奏すればするほどオーケストラは力を蓄え、さらに新しい楽曲の演奏がより早く、確実にできるようになる。人間の脳内にあるのは普遍的な言語習得能力ではなく、柔軟に成長する神経ネットワークのようなものではないか。新しい言語を習得すればするほど、ネットワークは広がり、緻密になり、強固になっていく。言語だけではない。学ぶということは脳の機能を変えてしまう力を持っているのではないか。
さて、私にとっては「リンク」は「張る」ものである。なぜなら、広がっていくことに意味があるからである。(「リンクを貼る」ではそこで止まってしまうではないか)。2024年11月にシリコンバレーを訪れた時、先端的なAIにいち早く対応したIT企業が必ず言っていたのが「優秀な人材の確保」であった。その際、組織内で育てるのでは間に合わない。世界中のネットワークを使って優秀な人材を探し出して連れてくる必要がある。グローバル企業の強みはここにもあったのだと実感した。
人それぞれに歴史があり、価値観も違う。自分の行動は、自分自身で柔軟に決めるべきだ。人間は「一人で生まれて、一人で死んでいく」ものなのだ。でも、そこにネットワークがあれば、孤独であっても決して孤立することはない。
自分の信念に従って行動する「高い志を持つ、市場価値の高い技術者」を育成します。
「市場価値の高い技術者の育成」を目指して、
コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

トップページ > コラム
柔軟性とネットワークが求められる時
2025.4.13