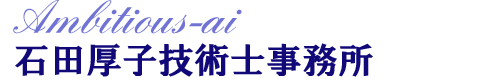高齢になれば好みが変わることがあるとしても、これは奇跡である。気づいたら、全くお酒(アルコール飲料)を飲まなくなっていた。何十年もの間、毎日晩酌を欠かさなかった。入院などしない限り、休肝日など全く設けていなかった。それが何の努力もせず自然に飲まなくなっていた。体にとっては良いことではあるのだが。なぜなのか。
この1年間の変化として思いつくのは、あまりお酒が美味しいと思わなくなったことである。何を飲んでも水で薄めたような感じがする。結果として飲む量はかなり減った。ただ、味覚がおかしくなったとは思っていない。コーヒーの味や香りの違いはしっかりと分かる。たまの外食で「美味しい」と感動もする。食事は決して残さないようにしている。
次に思いつくのが、お酒が入らなくてもよく眠れることに気づいたことである。これまでは、お酒を飲まなければ寝付けなくなるのではないか、という恐怖感を持っていた。ところが、飲まなくても夜10時過ぎれば眠くなり、11時近くなると寝床に潜り込んですぐに眠ってしまう。夜中に目覚めることも殆どない。飲む必要などないではないか。
そして、ひょっとしたらこれが最大の理由かもしれないが、物価の高騰対策として最も有効なのが「酒代を無くすこと」であるということに気づいたからである。すべての物価が上がる中で、出費を抑えることを追求してきた。その結果露わになったのが、アルコール飲料の費用だった。食費の中で相対的に突出して高いではないか。
無駄な出費と思われる固定費は、固定電話の解約、定期購読の雑誌の解約も含めてことごとく削減した。そもそも後期高齢者の私にとって、物は増やしたくない。衣類を含むモノに対する出費も削減した。しかし、生きていくために食べることは止めるわけにはいかない。生活費の切り詰め手段として最後に残ったのが、食費を抑えることだった。
まずは、外食、中食を避けてすべて自炊することにした。さらに、食品はできるだけ安いものを探し、見切り品は見逃さないようにした。野菜は捨てるところを極限まで少なくする。こうした努力を重ねた結果露わになったのがアルコール飲料の費用だった。高級なお酒など買わなくても、缶チューハイ1本で、キャベツの芯まで細かく刻んで食べている努力などふっとんでしまう。そもそもお酒を飲む意味は他人との会話を楽しみ、コミュニケーションを良くすることにあるのではないか。一人暮らしの私にとって晩酌に意味などない。
さて、ここまで来て、何もかも切り詰めていて一体何が楽しくて生きているのか、と疑問を持ちたくなるのだが、それは違う。何かを止める一方で新しいことを始めることもできる。例えば、半年前には内容に共感できずにNHKの朝ドラの視聴を止めていたのだが、今は全く違う。開始時間までに朝食を済ませ、必ずオープニングから背筋を伸ばしてしっかりと視聴している。時として感動で涙をこぼし、次の展開が心配で夜まであれこれ考えたりする。手作りの大福でおやつタイムを楽しむこともある。ガイドブックを見ながら鉄道旅の計画をいくつも作って行った気分になるのも楽しいものだ。
柔軟に生活を変化させられる私である。いつか、お酒を楽しむ日が戻ってくるだろう。
自分の信念に従って行動する「高い志を持つ、市場価値の高い技術者」を育成します。
「市場価値の高い技術者の育成」を目指して、
コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

トップページ > コラム
お酒を飲まなくなったのはなぜか
2025.6.22