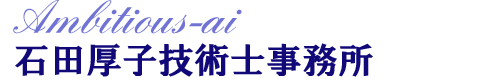下の子が11歳になった日から日記をつけ始めた。あれから30年以上続けている。10年日記が3冊となり、その後5年の卓上日記に変えた。最初は鉛筆書きで内容もメモ書き程度だった。そのうち、万年筆を使うようになり、内容も増えてきた。時々、その日と同じ日付の箇所とその周辺を読みながら、時の流れを感じたりしている。
ふとしたことがきっかけで、18年前の私自身の入院、手術のときの日記の記述を読み返した。そこには、あった事実が淡々と描かれているだけで、感想などの情緒的なことは全く書かれていなかった。しかし、思いもかけずその頃のことがまざまざと蘇ってきた。手術前に多くの人のアドバイスを受けていたこと。それで安心したり、不安になったりを繰り返していたこと。手術後、麻酔から覚めた時に子供たちがのぞき込んで私に呼び掛けてくれたこと。それが何よりうれしかったこと。退院の日に子供たちが車で迎えに来てくれたこと。車のちょっとした揺れで手術の傷口が痛んだこと。退院を祝って夕食やケーキを用意してくれたこと。退院した後も、休みの時に私に付き合ってくれて話を聞いてくれたこと。その頃の細かな事実や感情が、次から次へと記憶として湧き上がってきた。
特に驚いたのは、入院と手術の前後の日々の記述から、当時の自分がどれだけ家族に支えられてきたかが、強く感じられたことである。エッセイなどではなく日記帳の狭いエリアへのほぼ記録メモに近い記述である。わざわざ、いつも一緒の家族への思いなど書くスペースなどない。まして、手術後のつらさもあって、体も心もそういった感情を書く余裕もなかった。しかし、記憶にはしっかりと残っていた。記憶はやがて消えていく。10年以上前のことは殆ど覚えていない。しかし、記録が残っていれば、記憶を呼び戻すことは可能である。それを強く認識したひと時だった。
よく政治家が「記憶にございません」と言う。忘れていることはあるだろう。しかし、記録さえあれば、20年、30年以上前ならともかく、10年前ぐらいまでなら絶対に思い出せる。問題なのは、記録がない、あるいは記録をあえて破棄したことである。現在は、ITを使えば記録は容易である。しかも、場所を取らずに保管できる。記録を取って保管することを義務付けることによって「記憶にない」と言わせないことが必要だ。
記録が記憶を呼び起こすといったが、あくまでもそれに直接携わった人の記憶であって、無関係な人の記憶が蘇るわけではない。だからと言って記録がそれらの人たちにとって無意味ということではない。むしろ、無関係な人に物事を伝えることにこそ記録が重要な役割を果たす。その一つの例として話題になるのが、先人の知恵、技術を記録して、次の世代の人に伝えることがある。これは長年、技術の継承の手段として取り上げられてきた。しかし、人から人へ伝えるということには技術の進歩を滞らせるという面もあるのではないか。
先人の技術はAIに伝えてロボットで実現してもらいたい。次の世代の人は、むしろ、先人の知恵や技術に囚われるのではなく、もっと違うやり方を創り出してもらいたい。記録に残る価値は消えないのだから、それで良いのではないか。
自分の信念に従って行動する「高い志を持つ、市場価値の高い技術者」を育成します。
「市場価値の高い技術者の育成」を目指して、
コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

トップページ > コラム
記録は記憶を呼び起こす
2025.2.9