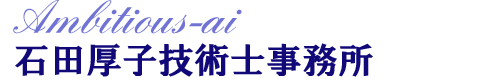2025年が始まった。1年前に何を考えていただろうかと2024年のコラムを読んでみた。そこで気づいたのだが、AIというものに対して危機感を抱いていたようだ。その反動か、人間の能力がAIよりも優れていることを何度も書いていた。ところが、次第にAIへの見方が変わって来ている。現在の世界および自分自身が抱える問題をAIに解決してもらいたい、という気持ちが強くなっているのである。最新技術の進歩は人間の意識の変化のスピードも変えている。さらに、大きく変化しているものがあることにも気づいた。
最近、多くの業界における企業のM&A、企業買収、統合、連携の報道が増えている。業界の再編にまで進んでいる。しかし「規模の拡大による効率向上、市場拡大」を目的とした統合は以前からあり、合従連衡という言葉が盛んに使われていた。どこが違うのか。その時に思い至ったのが、「規模の拡大から価値の拡大へと変化」ということだった。
これまでの規模の拡大は、各企業の持つ「要素」を加算して積み上げることが主体になっていたのではないか。相乗効果による価値の拡大を狙っていたとしても、結果として既存のものの足し算に終わっていた。例えば、要素として次のものが考えられる。
・技術 ・人材 ・市場
しかし、これらの組み合わせから効率向上により収益を上げるということを目標にしていても、新たな価値を生み出すところまで至っていなかったように思える。これから目指すのが「価値の拡大」であるとしても、その要素は基本的に変わらないと思う。しかし、「価値の拡大」に結びつけるには、各企業の持つ「要素」の中身と量をよく調べ、相乗効果のある組み合わせを考えて、そこからどういう新たな「価値」を見出すかまで考える必要がある。そこで要素に2点を加えた。市場以外の各点について具体的に述べる。
・データ ・技術 ・人材 ・ノウハウ ・市場
①データ:過去に蓄積された大量のデータ。公開されていないものに価値がある。生成AIの学習データとして使うことにより、他社にない知識を生み出すことができる。②技術:これまで蓄積されてきた技術と先進的な技術。これらを組み合わせることにより、新たな強みの発見、適用分野の拡大にもつながる可能性がある。
③人材:スキル、レベル、数、多様性(地域、言語、性別)など最も相乗効果から価値を生み出す可能性のある要素である。人材をコストではなく資産と捉えるべきである。
④経験、ノウハウ:企業を取り巻く環境は複雑で流動的である。これまで経験したことのない事態が襲ってくる可能性が高い。自らの経験だけで対処することは困難である。他地域の他社の持つ経験(リスクマネジメント、失敗事例など)は貴重である。
この中で最も難しいのが③の人材の価値拡大かもしれない。例えば、これまで蓄積された技術の継承と新しい技術の導入は別物として捉えられてきたのではないか。これを融合することで新たな価値を生み出せたら、人材こそ最大の資産と言えるのではないか。 価値を生み出す企業統合の増加で日本の経済に大きな上昇があることを期待したい。