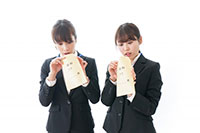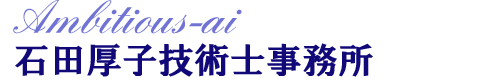2025年6月初めは、コメの価格高騰に対処するために政府が備蓄米を放出し、それが迅速に大手スーパーやコンビニに並ぶようになったニュースで溢れかえっている。備蓄米の放出は何か月も前から行われていたが、一般庶民のところまで殆ど届いていなかった。それが、担当する大臣が変わったら急に届くようになったのが驚きということである。スーパーの開店前に何千人もの人たちが並んでいる光景は、地元のスーパーで行われる卵の特売や野菜の詰め放題で人が殺到するのに似ていて、よく考えると異様である。
同様に、この春のニュースとして、人手不足の影響か新入社員の初任給が大きく上がっているというものがある。それだけ優秀な人材の取り合いになっているのか。確かに、技術の進歩やビジネスの変化のスピードに対応できる優秀な人材を確保するのは難しい。海外の人材を採用すればとてつもない給与を払わなければならないので、初任給を上げるくらいは大手企業なら何でもないことなのだろう。ただし、やるべき重要なことは他にある。
格安でも、高給でも、見た目の額に人は飛びついてしまう。でも、あくまでもこれは初期値であり、一時的なものである。その後、上昇か下降かのどちらに進むかを保証するものではない。備蓄米が尽きれば放出は止まり、コメの値段は元に戻る。反動でさらに高騰するかもしれない。初任給も同じである。初期値が高いからと言って、その後の伸び率も高いとは限らない。これから数十年働くことになるのだ。歓迎されてドアを開けて中に入ったら断崖絶壁、ということだってあるかもしれない。我々は、一時的な見た目のインパクトに踊らされず、その先のことを冷静に考える必要がある。
私が就職した50数年前、初任給は急上昇していた。前年、前前年に入社した人の初任給が自分よりかなり低かったのでびっくりしたことを覚えている。しかし、その後の昇給も今では信じられないほど大きかったので、入社年度の違いによる世代間の摩擦は殆どなかったように記憶する。ただし、沸き立っていたのはバブルの時期までで、それが弾けると、給料は上がるものだという認識が大きく変わった。ヒラから管理職になっても、さらに昇進しても、全然給料が上がらなくなったのである。つまり、肩書が変わっておめでとう、という紙一枚だけのことになってしまった。日本の経済が伸びなくなったからに他ならない。
それでも、私たち団塊の世代はまだうまく逃げ切れたのかもしれない。私たちの子供の世代は就職氷河期世代である。初期値もその後の伸びも低い気の毒な世代である。それに続く世代は、人手不足で一見すると就職市場では歓迎されているようだが、あくまでもこれは初期値である。これから日本の経済を上昇にもって行かなければ、試練が待ち受けていることは明かだろう。もっと生産性を上げて、もっと豊かな国にしていく努力を期待したい。
備蓄米が美味しいかどうかが話題になっているが、問題の本質からは遠い。今は、根本的に日本の食料問題を考える時ではないか。人それぞれに事情は異なるが、共通しているのは、安定的に食料が行き渡ることだろう。私も、地震などが起きた時に備えて、長期保存できる食料を備蓄しているが、個人の努力には限界がある。将来を皆で考えなければならない。
自分の信念に従って行動する「高い志を持つ、市場価値の高い技術者」を育成します。
「市場価値の高い技術者の育成」を目指して、
コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

トップページ > コラム
備蓄米と初任給
2025.6.8